- REPORT
【じょうもう今昔物語】
建築家と「臨江閣」を歩く-。近代前橋の繁栄と苦難の歴史を見つめた名建築と語らう【湯けむりフォーラム×上毛新聞】
1887(明治20)年の創刊以来、群馬県内のニュースを伝え続けてきた地元紙「上毛新聞」。約140年分の歴史が詰まった紙面のデジタルアーカイブをひも解けば、まちの過去と人のつながり、先人たちの思いが見えてくる。
今回は、近代日本における前橋の象徴的な建築物として、和風建築「臨江閣」をテーマに、県都の歴史とまちづくりの歩みを過去記事と共にたどる。
・・・・・・・・・・・
・上州の山河が一番のもてなし
・本館と茶室、官民連携の「起点」
・市民が「使える文化財」として継承
・アートで過去と未来をつなぐ
臨江閣(前橋市大手町)は群馬県庁の北側、名の通り利根川の流れを臨む場所に建つ。
本館、別館、茶室の3棟があり、いずれも明治期の建築。県都の繁栄と苦難の歴史を見守ってきた臨江閣は、前橋の今にどのような影響を与えたのか。建築史家の臼井敬太郎さん(47)=前橋工科大学専任講師=らと歴史ある空間を歩き、名建築が現代に投げかけるメッセージを読み解く。
上州の山河が一番のもてなし
日本庭園が色づきはじめた2023年11月、臼井さんと建築家の石黒由紀さん(55)=前橋工科大学准教授、志賀辰哉さん(24)=同大大学院生=とともに臨江閣の正門をくぐった。
まず目にするのは、木造2階建ての本館と別館。近代和風の格調高い外観は、訪れた人に県都の風格を感じさせる。
前橋の近現代史と建築の関係に詳しい臼井さんは「臨江閣は歴史や文化交流の起点となる重要な建築物」と強調する。「明治時代には要人を迎える迎賓館の役割を担い、前橋における鹿鳴館と言える。鹿鳴館は日本の近代化をアピールするため西洋風に造られたが、臨江閣は和風建築にこだわった点に注目したい。利根川や妙義山、浅間山など群馬らしい景色、地元の優れた木材と建築技術を生かしており、群馬県を代表する建築文化だ」と力説した。

1884(明治17)年建設の本館は、群馬県の初代県令、楫取素彦(1829-1912)とゆかりが深い。楫取は幕末の長門国萩(現山口県萩市)生まれ。吉田松陰と親交が深く、松陰の妹、文(ふみ)を妻とした。1876年に第2次群馬県の初代県令(知事)となり、養蚕や製糸業など産業の発展、教育振興に貢献し、近代群馬の礎を築いた。
-1-1034x1140.jpg)
臨江閣の建設は、楫取が県令就任直後に取り組んだ「県庁移転」に端を発する。
当時の県庁は高崎に置かれ、1876年9月から安国寺(高崎市通町)などで執務が行われた。ただ次第に手狭となり、庁舎分散による不便さもあって、1カ月ほどで前橋の仮庁に移転。背景には、後に初代前橋市長となる下村善太郎(1827-1893)ら生糸商人の熱心な誘致活動があった。
当時の前橋は製糸業で栄え、生糸商人には潤沢な資金があった。県庁移転の際も、下村ら地元有力者が楫取の意向をくみ、庁舎や官舎を準備した上で多額の準備金を寄付した。
1881年の太政官布告で、前橋を県庁とすることが正式決定。当時の前橋には皇族や高官をもてなす場がなかったため、楫取が「迎賓館」の必要性を訴えた。ふたたび下村らが土地や資金を提供し、旧前橋城の一角に臨江閣本館が建設された。

本館は木造二階建て、上下階の各所に座敷を設けた。1893年には明治天皇が滞在し、大正天皇も皇太子時代に1902年、1908年と2回にわたって訪問。当時の上毛新聞は、御座所となった2階の「一の間」について紹介した記事で、特に眺望の美しさを称賛している。
「御障子を明(あ)くれば正面は閣(かく)の名の如く利根の激流に臨み眼を放てば榛名妙義の山は悉(ことごと)く一眸 (いちぼう)の中にあり」。
-1-1140x258.png)
石黒さんは館内を巡りながら「当時のつくり手たちは、窓から見渡す上州の名勝を誇りに思い、来賓への一番のもてなしと考えたのだろう」と語った。「本館は日本の建築様式の一つ、数寄屋造りが特徴。数寄とは茶事や風流を指し、茶室に通じる美意識が建築デザインに取り入れられている。シンプルでありながら、周囲の景観をうまく生かしており、訪れるたびに発見や問いかけを感じることができる」

本館と茶室、官民連携の「起点」
本館と同じ年に建てられた茶室は、庭園の奥にひっそりとたたずむ。通常は内部を公開していないため、本館や別館に比べるとその存在感は薄い。
大学院生の志賀さんは茶室のつくりに興味を持ち、実測調査を基に展開図を作成した。研究を進める中で、特に茶室の天井と窓からの景色に心ひかれたという。

「よく見ると、茶室の天井には段差がある。貴人口の近くは掛込天井(かけこみてんじょう)で高さを出し、点前側を低くすることで下座を示している。客を敬う気持ちを示す、茶室ならではの造り。外の腰掛に座ると、袖壁の枠にくっきりと切り取られた景色を楽しめる。周囲の景観を美しく見せ、訪問者を楽しませたいというつくり手の思いは、臨江閣全体に共通する理念だと思う」(志賀さん)

臼井さんは、茶室や本館が官民連携で作られた歴史に注目する。本館建設への市民の惜しみない協力に感動した楫取と県庁職員らは、その返礼として、資金を出し合って茶室を贈ったという。「当時の市民たちは公共事業に私財を投じ、街の発展や市民の幸福に貢献していた。現代の前橋でも『めぶく。』ビジョンの下で民間主導のまちづくりが進むが、その根底には臨江閣に共通した思いがある。まちづくりの原点は誰かを幸せにすること。臨江閣は、市民一人一人がまちのために行動するという『めぶく。』ビジョン(2016年に発表された前橋市まちづくりビジョン)の起点であり、そして前橋における官民共創の起点でもある」
県庁所在地となった前橋は、1892年に「前橋市」となり、関東で4番目、県内で最初の市制が施行された。製糸業の繁栄とともに都市として発展し、1910年の群馬県主催「一府十四県連合共進会」の開催を機に近代化が加速。市内の大通りには電灯がともり、鉄道や道路の整備へとつながった。
共進会は、国による殖産興業政策のもと、主に地方産業を発展させるために全国各地で開催された品評会。展示会や博覧会的な意味合いもあり、前橋の高品質な生糸を売り出す絶好の機会となった。
-1-1140x965.png)
臨江閣・別館は共進会の貴賓館として、開催の約1カ月前に完成した。木造二階建て、入母屋造り、桟瓦葺き、書院風建築。本館は伝統的な和風建築であるのに対し、別館は大空間を実現するために床組を鋼材で補強するなど、近代的な構造手法も取り入れた。

共進会開催当日の上毛新聞は、完成した別館について「階上百八十畳柱なしの大広間は慥(たし)かに珍とすべし」と評した。また「宏壮(こうそう)たる貴賓館」「貴賓を待つに絶好の位地 絶好の建物なり」とたたえ、前橋の新たなシンボルへの期待を込めた。
共進会後、臨江閣は市の公会堂として利用され、広く市民に親しまれた。市民向けの講演会や懇親会といった大規模集会の会場となり、現在に至るまで県内外の政治・経済分野の人材交流や文化振興、海外からの来客者の迎賓館としての役割を担っている。
-1-1140x590.png)
市民が「使える文化財」として継承
1945(昭和20)年8月5日、前橋市は米軍による大規模な空襲を受けた。市街地の8割は焦土となり、戦死者は県内最多の535人。惨劇のわずか10日後に日本は終戦を迎え、戦火を免れた臨江閣は1954年まで仮市庁舎として戦後復興の拠点となった。
-1-1140x746.png)
国を挙げての経済復興、そして高度成長期へ。1983年に群馬県で開催された国民体育大会「あかぎ国体」では、前橋市がメイン会場となり、大会に合わせて上越新幹線や関越自動車道などの交通網や都市整備が加速した。
一方で、臨江閣は存続の危機に直面する。老朽化を理由に取り壊し、跡地に新たな公民館を建設する案が浮上。中央公民館や市民文化会館など、新たな文化活動拠点が誕生したことで、存在意義が問われるようになった。
-1043x1140.png)
前橋市教育委員会は、臨江閣の保存活用を考える検討懇談会を設置し、協議を重ねた。
上毛新聞は1982年4月19日付の記事で「懇談会は、臨江閣は市にとって躍進の基礎を築いた重要な建物で、明治時代の精神の象徴として長く保存する必要性を訴えている」と報じ、今後は資料館として活用する方針と伝えた。
その後の調査で、臨江閣が文化史、建築学上の価値が高いことが分かり、1986年に本館と茶室が県重要文化財に、別館が市重要文化財にそれぞれ指定された。翌年から本館と茶室が保存修理され、2016(平成28)年からは別館の初の大規模な改修工事が行われた。
2年にわたる屋根の改修や耐震補強などを経て、2018年に3棟すべてが国重要文化財に指定された。
-1140x641.png)
国重要文化財となった後も広く市民に開放され、「使える文化財」として人気を集める。入場無料の観光スポットとして、またイベントやレセプションの「ユニークベニュー」(特別な会場)、市民による茶会や演奏会、和装の撮影スポット、有名人のミュージックビデオやドラマのロケ地としても活用されている。
2023(令和5)年4月、群馬県内で開催された先進7カ国(G7)デジタル・技術相会合では、政府関係者やG7など各国要人を歓迎する夕食会の会場として臨江閣が選ばれた。
令和の時代に、臨江閣がふたたび迎賓館として役割を取り戻した瞬間だった。
.jpg)
石黒さんは「臨江閣という『宝物』をしまっておくのではなく、誰でも見学できて、利用できることがすばらしい」と評価する。
自身の大学研究室でも、産官学で市街地の古民家をリノベーションする「広瀬川コート・中澤庵」プロジェクトを手掛け、学生向けシェアハウスやアートスペースとして活用している。「臨江閣を例にとっても、前橋は歴史的な建物に対する考え方がおおらか。広瀬川コートも前橋だから生まれた試み。古い建築はこう使うべきときっちり決めつけないから、活用の幅も広がる。その積み重ねが、前橋の街を面白くしている」(石黒さん)

志賀さんも建築を核にした前橋のまちづくりに共感し、卒業後は市内の設計事務所に就職する。「前橋だからできる建築がある。この街で、臨江閣のように住む人のアイデンティティーや地域の活性化につながる仕事がしたい」と意気込みを語った。
アートで過去と未来をつなぐ
臨江閣は現代美術の「実験場」として、国内外のアーティストからも注目を集める。
1993(平成5)年には、前橋市在住の美術家、白川昌生さんらが地域とアートをつなぐ美術団体「場所・群馬」を立ち上げ、翌年には臨江閣で同名の展覧会を開いた。臨江閣という日本的な「場」に着目することで、明治期の西欧化や戦争、格差など近代化の課題を鮮やかに表現した。臨江閣は、その後も「場所・群馬」の重要な展示会場となった。
-853x1140.png)
渋川市でアートギャラリーを主宰する現代美術作家、福田篤夫さんも「西洋の物まね」ではない現代美術の独自性を模索する中で、臨江閣という「場」に注目した。
1990年から、日本美術の流派、琳派と現代アートを融合させた展覧会「数寄者達-琳派以後の方法-」をスタート。国内外のアーティストとともに、琳派の作品や考え方をモチーフにした立体、平面、映像、写真などを展示してきた。
-1119x1140.jpg)
臨江閣を舞台に現代美術の可能性を探る取り組みは現在も続く。現代美術作家で福田さんの長男、周平さん(26)と嬬恋村出身の宮崎優花さん(33)は2019年から、茶室を展示空間としてとらえる「臨江閣【茶室】プロジェクト」に取り組んできた。
.jpg)
宮崎さんは「鑑賞者は畳の上に座ることで、ギャラリーや美術館では得られない、より深く密なアート体験が得られる。作家にとっても茶室のような狭く制約の多い場所に作品を置くことで、新しい展示の仕方を発見する機会になる」とプロジェクトの意義を語る。
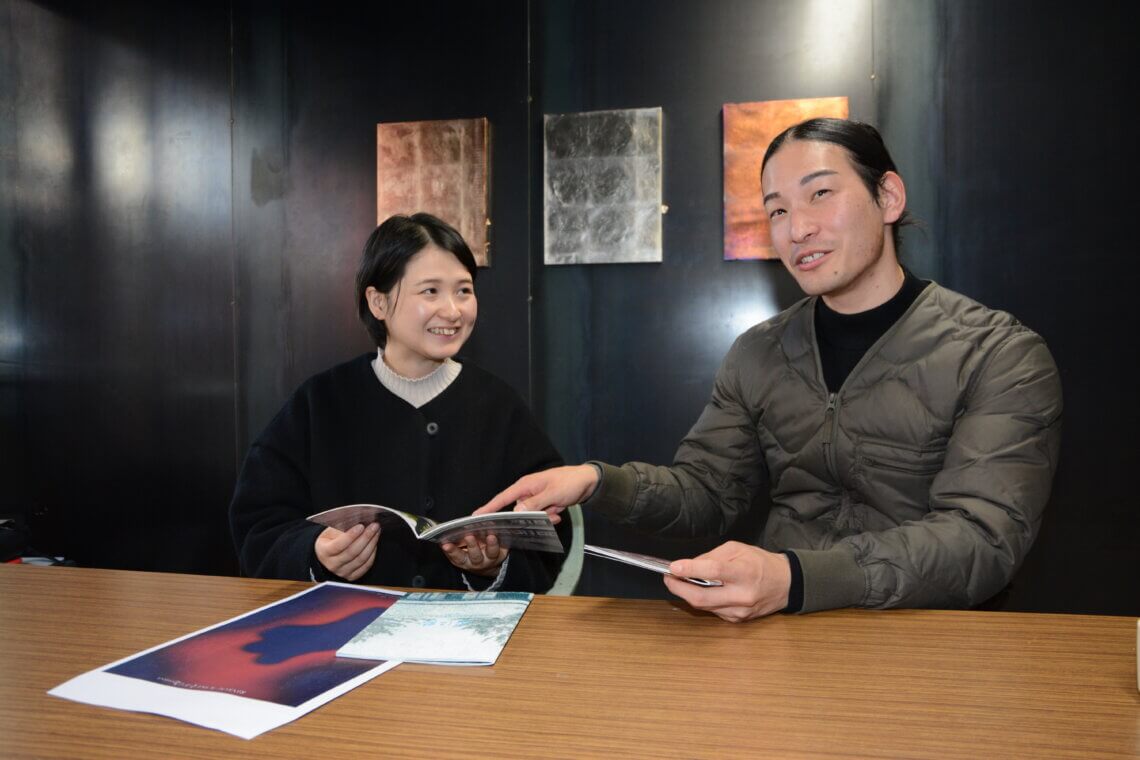
周平さんは茶室という日本の伝統建築を使うことで、グローバル化する社会の課題を表現し、新しい国際交流の場を作り出すことを期待する。「ソーシャルメディアやインターネットの普及で、世界中で時間や体験の同時性が高まっている。ただそれは表面的な感覚で、本当に深く対象を見ているわけではないと思う。茶室は外国人作家からの関心も高い。それは作品や人と深く対話できる茶室という場が、現代においては貴重で価値ある空間だと気付いているからだろう」
街にたたずむ建築たちは、私たちにどんなメッセージを伝えているのか―。
臼井さんは、歴史的建造物の魅力やあり方を伝えるため、さまざまな試みを続けている。グルメと建物巡りを楽しむガイドブックを制作したり、ライトアップを通じて平和のメッセージを発信したり。さらに、大学研究室の学生たちと協力して、市内の歴史的建造物の写真を基にイラストを制作している。

県庁昭和庁舎や群馬会館といった現存するもののほか、かつては洋風の造りだった前橋駅舎や麻屋百貨店、前橋商工会議所などが描かれている。「臨江閣のように受け継がれた建物もあれば、戦禍や開発で失われた建物もある。白黒の線画は構造をくっきりと示し、前橋がいかに優れた建築に彩られているかを教えてくれる。明治の時代から、前橋は文化や人が『めぶく』可能性に満ちた街だった―。近代建築と向き合うことで、私たちはそんな未来へのメッセージを受け止めることができる」(臼井さん)
取材日:2023年11月15日
制作:上毛新聞社
執筆:上毛新聞社営業局出版編集部 石田省平、同局デジタル営業部 和田早紀
撮影:上毛新聞社DX局メディア配信部 梅沢守
※臨江閣および日本庭園は、前橋市の許可を得て撮影しています。
